氷河期世代の逆襲 ― 管理職になった私たちが今、企業を支えている
派遣・成果主義・終身雇用の崩壊を超えて、“人を育てる経営”を再起動する世代

どうも、名ブタです。
今日は、氷河期世代の管理職について、真面目に話してみようと思う。
いま企業の中核を担っている管理職層は、まさに氷河期世代。
でも彼らのマネジメント力を疑問視する声が、時折聞こえてくる。
……それって、本当に当人の問題なんだろうか?
時代背景を無視して、「上に立つ者として未熟だ」と切り捨てていいのか?
僕は違うと思う。
■ 派遣:育成の土台を壊した
氷河期世代が社会に出た頃、日本では正社員採用が大幅に絞られ、代わりに派遣社員・契約社員が急増した。バブル後、非正規が急増した背景には国の雇用政策の転換があった。 この時代に若者として職場に入った者たちは、派遣であればワーカーとしての即戦力を求められ、教育も育成もされない。正社員ではないが故にシッカリとした教育を受ける機会に恵まれなかった。
仮に正社員として入社できたとしても、職場の同僚や後輩は派遣が中心であり、長期的に人材を育てるという視座自体が希薄だった。 つまり、教える経験もなければ、教えられる環境でもなかった。
そしてのちに派遣から正社員登用された人材も、既に"育つ時期"を逸していた。育成されないまま戦力化され、育てられなかった人が、次の誰かを育てられるだろうか?
■ 成果主義:育成を“損”に変えた
同時期に導入が進んだのが成果主義だ。外資の影響やバブル崩壊後の効率化志向により、企業は個人評価を強調した。
その結果、人を育てることが評価されなくなり、「部下を育てる」よりも「自分で成果を出す」ことが最も合理的な行動になってしまった。
育成には時間がかかる。成果にならない。教えた相手が出世すれば、自分の立場が脅かされる。 ──そうして、「育てる理由」が、社会全体から静かに消えていった。
■ 終身雇用の終了:信頼の前提が崩れた
かつての日本企業は、社員を一生守ることを前提としていた。その信頼があったからこそ、社員も会社に忠誠心を持ち、後輩を育て、仲間と共に組織を育てた。
しかし今は違う。会社は社員を守らない。社員も、会社に尽くす理由がない。お互いが「どうせ辞める/辞められる」前提で動くようになった。
その中で、「育てる文化」など生まれるはずもない。
■ プレイヤー能力だけは鍛えられた“異常環境”
皮肉なことに、氷河期世代はプレイヤーとしては歴代最強クラスだ。
人手不足、マルチタスク、IT変化、制度改定──すべてが一気に襲ってきた現場を、この世代は無理やり支え続けた。
部下も育たない。上司も消えた。自分一人で“全部回す”ことを強いられた。
そのスキルは、称賛されることなく「当たり前」として処理され、管理職になった頃には「育成力がない」と責められている。
■ 気づき始めた人はもう気づいている
CS(顧客満足)からES(従業員満足)へ、理念なき企業の限界、カスハラ拒否、社員を守る会社への共感──
今、日本は少しずつ“人を大切にする経営”へと回帰しつつある。
長寿企業のエピソードに見られるのは、苦しいときでも社員の給料を守った経営判断だ。 理念の力。信頼の蓄積。
経営の神様・松下幸之助が「企業は人なり」と言っている。
人を育てることは、企業を育てることにつながる。
この思想は古びるどころか、今こそ見直されるべき価値を持っている。
■結論:氷河期世代よ、誇りを持て
氷河期世代の中間管理職は、長年にわたって苦労をしてきた。
しかし、今、企業の中核を担う立場として着実にその実力を発揮している。
従業員満足(ES)が重視され始めたのも、まさに氷河期世代が管理職として頭角を現しはじめた頃だ。
カスタマーハラスメントへの毅然とした対応も然りだ。
プレイヤーとして、そして管理職として多面的な苦労を重ねてきた我々だからこそ、現場と組織を同時に守る行動が取れているのだ。
苦しい時代を生き抜き、派遣・成果主義・終身雇用崩壊という波に揉まれながらも、なお組織を支える柱として立ち続けている氷河期世代。
我々のマネジメント力を、誰にも疑わせるな。
名ブタでした!









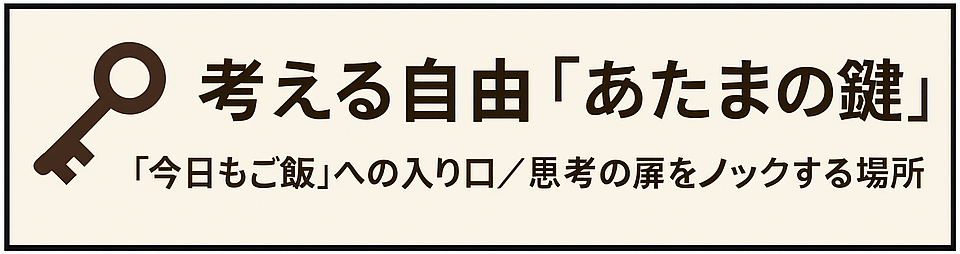
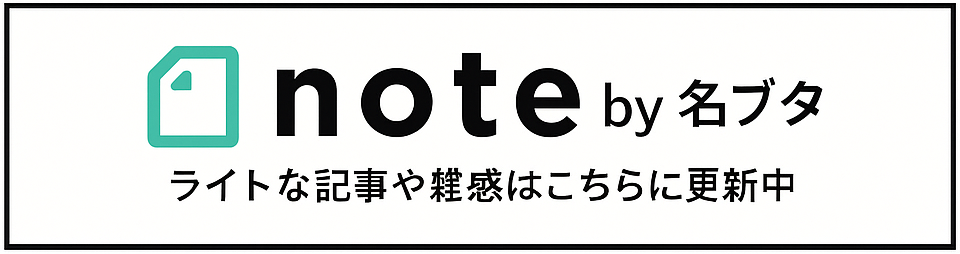
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません