最低賃金について考える。――景気操作と一律化による地方活性化の可能性
ー 幽霊企業すら糧にして地域の税収と人口を増やせ

どうも、名ブタです。
政府が最低賃金を毎年のように引き上げてるよね。
でも、今の物価高は円安や原材料高によるコストプッシュ型インフレ。
企業の利益が増えているわけじゃなく、むしろ維持するための値上げ。
そんな中で最低賃金をさらに上げるのは、企業にとっては負担増。
結果は人員削減や価格転嫁、つまり失業増加やさらなる物価上昇につながる可能性がある。
「これって逆効果じゃないの?」という違和感を覚えたわけです。
最低賃金ってどういう時に上げる?
そもそも最低賃金はどういうときに上げるのか?
物価調整の装置としては機能する可能性はありそうだ。
-
デフレ時(需要不足) → 最賃を上げれば消費を喚起できる
-
インフレ時(需要超過) → 最賃を下げれば消費が冷えて物価が落ち着く
つまり、最低賃金は「需要操作のレバー」として使えるかもしれないんだよね。
でも、下げられない
ただし現実的に考えると、政治家は最低賃金を下げられない。
票を失ってしまうからね。
理屈では可能でも、実際には“上げるしかできない一方通行”になっている。
ここに今の日本の政策の限界があると思ったわけだよ。
そもそも、最低賃金って最低賃金以上で働く層も居るから、最低賃金が変動しても給与に変化の無い人がいる。
そういう人たちは単に物価に右往左往することになるけど、消費行動がどう変化するか予測が難しい。
景気刺激したきゃ別の手段
供給する側の企業が影響を受ける最低賃金操作は景気操作の意味が薄い気がする。
ってなると景気操作をしたい場合は企業が影響を受けない方法でしないといけないから、
- デフレ時(需要不足) → 国民に現金・期限付きクーポン・電子マネー等の給付
-
インフレ時(需要超過) → 金利を上げる
なるほど、デフレ脱却だと叫びながら消費税を上げる自民党のおかしさが理解できたw
それはいいとして(良くないけど)、現金給付って政府やってるじゃん?って思うよね?
でも、この給付ってのはトリガーを設けて継続しないと意味がないと思うよ。
だって、いつ給付するか解らない計算できない需要に対して企業が行動するわけないからね。
だから政府のやってることは意味がないと思うわけ。選挙対策としか思えない。
それはそれとして、最低賃金について、もう少し話をしたい。
最低賃金の地域差について考えてみたんだ。
最低賃金って地域差をつける意味あるのか?
景気刺激策として最低賃金については何となく僕の中で整理ができたわけだけど・・・
ここまで考えて、以前から思ってた疑問が頭をもたげたわけ。
「そもそも最低賃金が地域ごとに違うのって合理的なの?」と。
地域による物価差などを反映しているという理屈はわかるけど、
リモートワークや転勤、トラックの長距離ドライバーのように、労働者は地域をまたいで働く時代。
「県境を越えたら保障額が変わる」というのは、もはや不自然。
だったら全国一律最低賃金にした方が公平じゃないか。
最低賃金を一律にしたら何が起こる?
地方へ人が移動する可能性があり。
-
同じ稼ぎなら物価の安い地方の方が豊かな生活ができるかも
-
多少稼ぎが落ちても地方の方が物価が安いので現状の生活レベルを維持できるかも
このような考えを持つ人が一定数でてくる可能性があって、都市部から地方への移住が発生するんじゃないか?
そこで発生するのが、地方における雇用の受け皿問題。
地方に人がやってきても就業場所が無ければ意味を成さない。
ってことは最低賃金を一律にするというのは、この問題解決もセットで行う必要がある。
単純に考えれば、地方の企業が得をする制度を導入すればいいという事になる。
全国一律と地方優遇の仕組み
そもそも、最賃を全国一律にするという事は、地方の中小企業は負担が増える事になる。
最賃が上がっても企業の売上が増えるわけじゃない。
だからここで必要なのは税制での調整です。
-
社会保険料の事業主負担を地域係数で調整
-
法人税を段階的に変える
-
優遇は還付方式にして、条件を満たした企業に後から戻す
単純に地方の方が企業が有利にすれば、企業の都市部集中はさけられるかもしれない。
でも優遇目的の幽霊企業が増えたり、過剰に誘致をする自治体がでてくると、自治体格差が広がるかもしれない。
だから、従業員数とか、地域の労働人口などにキャップを設けて、それらに応じて、税率を段階的に調整するとか有りかなと考えた。例えば、地域で一定の枠を超えたら税率が上がるみたいな。そうすれば、メリット目的の幽霊企業も地方に分散するかもしれない。
幽霊企業は駄目だろ?
って思うかもしれないけど、僕は割り切ってもいいと思ってる。
幽霊でも“登記”が増えれば、自治体の税収が増えて財源強化になる。
それを使えば公共投資するなり、地方の活性化につながる政策が打てる。
でも、野放しは良くないから、違法とはするけどね。
あと、長年地域に貢献してきた企業には、累積納税額や営業年数を基準に別途優遇を与えれば、地域にとって大切な企業が逃げちゃうことも防げそう。
あくまでアイデアの断片
前項のアイデアは、綿密に組み上げたわけじゃなくて、例えばの一例に過ぎないけど、色々考えてると色々な問題が出てきて、それを考えるのは結構楽しかった。
ざっと覚えてるの上げてるとこんな感じ。
-
適性雇用枠:労働人口に応じて地域で必要な雇用総量を算出して、超えると税率が上がる。
- 社会保険料軽減:事業主負担分の社会保険に優遇が受けられる。
-
段階的税率:枠を超えた部分は税率を上げる。
-
還付方式:税を先に納め、条件を満たした企業には還付
-
優遇人数の上限:1社が優遇を独占しないように制限
-
長期貢献企業の優遇:納税・営業年数・雇用実績で評価
-
10年ごとの見直し:人口変動に応じて枠を再設定
- 特定企業優遇:地域から一定の雇用を生むことを条件に、さらに優遇
-
生活実態チェック:住民票+ライフラインで“偽装移住”を防止
まぁ財源がどうとかあんまり考えてないです。でも、人口減少が進みすぎてんだから、思い切ったことしないとジリ貧ですよね。
そうだ、社会保険に関してだけ、補足をさせて欲しい。
社会保険って発生した給与に対して発生するから企業がズルしづらいと思う。
蛇足の疑念
最後に蛇足ですが。
政府はガンガン最低賃金を上げ続ける方針です。
でも実際には、コストプッシュ型インフレ下で最賃を上げても効果は薄い。
そうじゃなくても効果なさそう。
では、誰が一番喜ぶのか?
僕が疑っているのは、外国人労働者です。
母国に仕送りをしている人たちにとっては、日本での最低賃金が上がればその分だけ換算できる外貨が増える。
国内での消費に回らない分、むしろ間接的な海外援助になっている可能性もある。
そう考えると、今の政策が誰のためなのか、ますます気になってしまうのです。
名ブタでした。









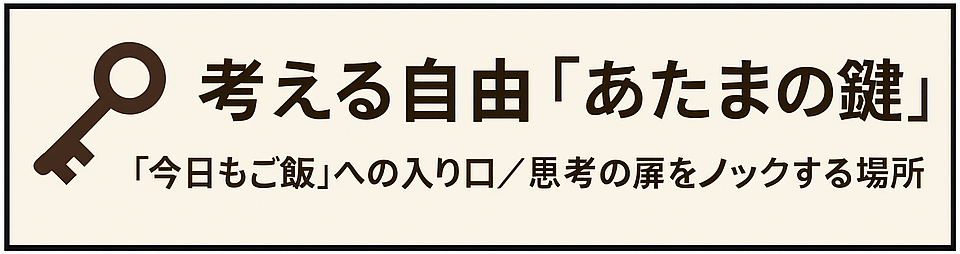
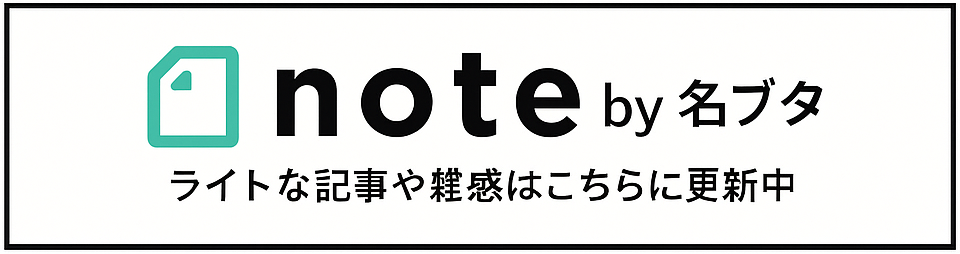
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません