世界は変化に満ちている
― 優劣の外にある“意味”を探して

どうも、名ブタです。
今日は少し、世界の見え方の話をしてみようと思う。
優れている=選ばれる、とは限らない
僕たちはつい、自分が何かに勝っていると感じると、それがそのまま価値であるような気がしてしまう。社内で評価されている、自分の方が能力が高い、そんな確かな実感があるときに、つい「自分の方が上」と思い込んでしまうのは、ある種の本能かもしれない。
だけど、それって本当に「上」なんだろうか?
たとえば、「どっちが好き?」って聞き方をすれば、まったく違う答えが返ってくるかもしれない。
能力的に完璧な人がいたとして、人格まで完璧だとして、それでも僕はきっと昔からの友人と遊ぶ。バカで、下品で、でも僕の人生に染み付いてるような、そういう友人と過ごす時間の方が、僕にとっての意味があるから。
つまり、能力や評価の軸では見えない「価値」が、この世界には山ほどあるということだ。
レベルの話ではなく、視点の話
これは人間関係の話ではなく、むしろ「どう世界を見るか」という話だ。
僕は最近、キーガンの発達理論をもとに、自己や他者の認識構造をよく考える。
-
レベル3では、他人の価値観に影響される自分がいて、
-
レベル4では、自分という軸が確立される。
-
そしてレベル5になると、その自分すら相対化されて、他人の物差しで自分を測ることができるようになる。
ここで大事なのは、
相手を自分の基準で測ることと、相手の基準で自分を測ることは違う、ということ。
前者はまだ、自分が中心だ。でも後者は、相手が違う見方を持っていると理解し、それを一度、自分に取り込んでみる視点。そうすると、「常識外れは自分かもしれない」という思いにたどり着く。
虹は同じでも、意味は変わる
世界は変化に満ちている。
今日見た虹と、明日見る虹は同じに見えて、たぶん違う。
あの日の虹が綺麗だったのは、あの日の僕がそこにいたからであって、今の僕がそれを同じように感じるとは限らない。
だから、意味づけというのは常に流動するし、「正しさ」もまた、絶対ではない。
自分を知るための“他者”という鏡
自分が優れていると信じることは悪くない。だけど、それだけじゃ世界は測れない。
僕たちは、自分が何者かを知るために、 ときに他人の物差しを借りて、世界の色を塗り替えていくんだ。
それが、僕が今、弁当を食べながら考えていたこと。
それと同じように。他者から見た虹もまた、自分とは違う別の顔を覗かせているだろう。 この違いを理解を超えて感覚として持てるようになったとき、 あなたは今より高次の扉の先に立っているだろう。
ごちそうさまでした。
名ブタでした。


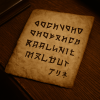





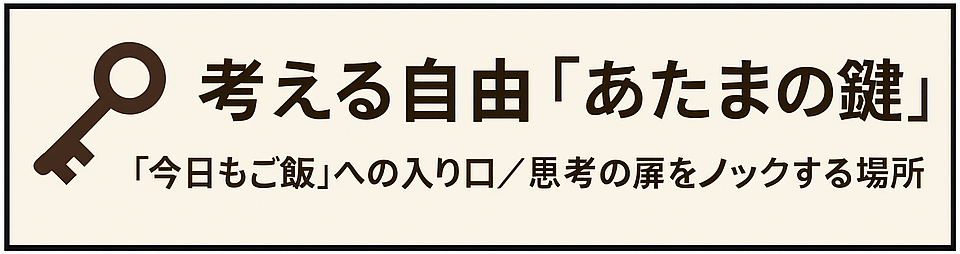
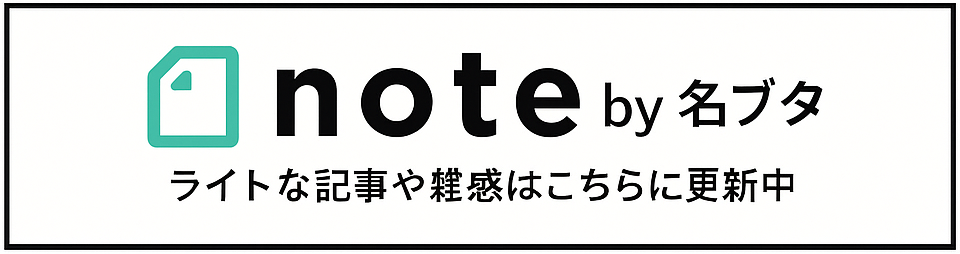
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません