農地と技術は国の命──移民が奪う日本の基盤

どうも、名ブタです。
今回は農業と土地の話。僕がずっと「国家インフラ中のインフラ」だと考えてる分野だよ。
水道や電気より先に大事なのは「食べ物」。だから農地をどう扱うかは、そのまま国の命運を左右する。
2025年4月の規制強化
今年4月、農地制度が大きく改正された。
ポイントはこんな感じ:
-
貸借制度の見直し:農地バンク(中間管理機構)を通す方式へ移行。
-
利用権設定の廃止:地域計画がある場所では旧来の直接貸借を封じる。
-
許可チェック強化:農業委員会が品種権侵害や法令遵守を審査。
-
外国人取得の制限:短期滞在者は対象外、在留資格や居住実態を厳しく見る。
-
転用規制強化:住宅地や商業地への転用もさらに制限。
ぱっと見は「規制強化」って感じで安心しそうだよね。
でも抜け穴は残る
実際にはまだまだぬるいと思う。
-
永住者や定住者なら一代目の移民でも農地取得が可能
-
法人スキームを使えば、日本人名義で実質外国資本が農地を握れる
-
地域計画がないエリアでは旧制度が残る
-
自治体の裁量差で、厳しく見る所と甘い所が分かれる
つまり「法律上の砦」はあるけど、門番が眠ってたら簡単に突破されるわけ。
技術流出は国の切り売り
シャインマスカットの例は象徴的だ。
20年かけて開発された品種が海外に流出して、中国や韓国で栽培されている。
見た目が同じなら消費者は安い方に流れる。
これは「農業技術=国の財産」を、無防備に切り売りしてるに等しい。
そして農業労働に外国人を大量に入れれば、同じことが起きるのは目に見えてる。
農村は盗むチャンスの宝庫になりかねない。
イスラエルの例に学べ
歴史を振り返ると、ユダヤ人が農地を基盤に共同体を築き、やがて国家を樹立したイスラエルのケースがある。
最初は「土地を貸すだけ」「農業をやってもらうだけ」だったのに、気づけば強固なコミュニティを作り上げ、建国に至った。
もちろん日本は同じ歴史をたどるとは限らない。
でも「土地を渡すこと」「農業を任せること」が、単なる労働力問題ではなく、民族的基盤をつくる行為になり得るという教訓は無視できない。
結び──ぬるい規制では未来を守れない
政府は「規制を強化しました」と胸を張るけど、実際にはまだまだ甘い。
抜け穴はいくらでもあるし、自治体次第でどうにでもなる。
農業と土地は一度手放せば取り戻せない。
イスラエルの例を知っているなら、日本はもっと警戒すべきだ。
農業は産業じゃない、国の命だ。
それを安直に移民に委ねることは、未来の自殺行為になる。
名ブタでした。







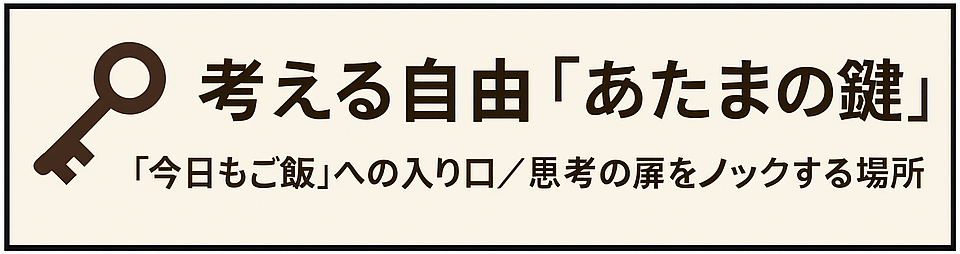
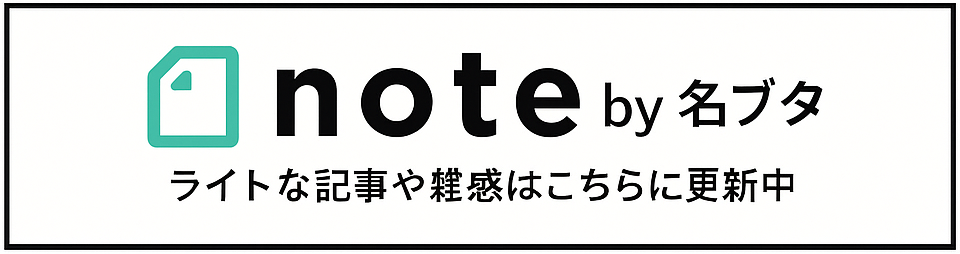
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません