ドラえもんを夢見なくなった国に技術は生まれない
イノベーション大国・日本の誇りと、製造業回帰の道

どうも、名ブタです。
最近よく耳にするのは「日本からはイノベーションが生まれない」という言葉だ。確かにスマートフォンやSNS、AIの分野ではアメリカや中国に後れを取っているように見える。かつて世界を席巻した日本メーカーの名を、今ではほとんど聞かなくなったのも事実だ。サンヨーもフナイもオンキョーも姿を消し、シャープですら外国資本に頼る存在となった。こうした現状を見れば「日本はもう終わった」と思う人が出るのも無理はない。
だが、果たして本当にそうだろうか? 日本はそもそも「ゼロからの発明」ではなく、既存のものを徹底的に磨き上げ、発展させることで新しい価値を生み出してきた国であるように感じる。0から1を作るよりも、1を5に、5を10にしてしまう力こそが日本の真骨頂とも言う。
だが、本当にそれだけなのだろうか?
日本はイノベーション大国だった
iPhone が世界を変えたと言われるが、その前に日本にはガラケーがあった。メール、カメラ、インターネット、おサイフケータイ、ワンセグ、防水機能――これらを一つの端末に詰め込んで日常生活の一部にしたのは日本の携帯文化だ。世界からは「ガラパゴス」と揶揄されたが、むしろ常識外れの進化を可能にした狂気的なイノベーションだった。
さらに遡れば、Apple は Newton という PDA を1993年に出していたが、日本には同時期にシャープの「ザウルス」が存在していた。カシオの「カシオペア」はさらに前だ。iPod が流行する前にはソニーのウォークマンがあった。つまりイノベーションとは常に既存知の延長線上にあり、日本はその先陣を切って挑戦してきたのである。
ガラパゴスは失敗ではない
「世界標準から外れたから失敗だ」と片付けられることが多いが、それは短絡的だ。ガラケー時代の日本には、世界が称賛するジョブズ一人分に匹敵するような“小さなジョブズ”が無数に存在していた。メーカーごとに独自機能を競い合い、ユーザーもまたその違いを楽しんでいた。売り方が下手で、時期が早すぎただけで、本質的には誇るべき創造力だったのだ。
いや、ちょっとやりすぎちゃっただけさ☆
技術は妄想と失敗から生まれる
技術というのは、効率や計算だけで育つものではない。数限りない試作と失敗を重ね、そこから磨かれていくものだ。だからこそ「妄想する心」が欠かせない。
ドラえもんが存在しなければ、誰もドラえもんを作ろうと思わない。妄想があるから作ろうとし、作るから技術が磨かれる。 この精神こそが、日本が長く持っていた「作るスピリット」である。
なぜ日本は力を失ったのか
ではなぜ、かつてイノベーション大国だった日本がここまで弱体化してしまったのか。理由は単純で、政策が国内の土壌を壊したからだ。
グローバル化という名の下に、国内よりも海外を優先する方向へ舵を切った。安い人件費を求めて製造業は海外に流出し、その結果、部品産業や人材育成の基盤も一緒に崩れた。技術水準そのものが芋づる式に落ち込んでいったのである。効率や国際協調ばかりを重視して、「作るスピリット」に対して十分な支援を行わなかったことが最大の誤りだった。
技術立国を取り戻すために
世界に誇れる日本を取り戻すには、妄想を許し、挑戦を支える土壌を築き直さなければならない。そしてそのためには――製造業を国内に回帰させることが不可欠だ。
製造業が戻れば、部品メーカーも人材も国内に循環し、技術の血流が再び蘇る。国内で試作と失敗を繰り返す余地があってこそ、新しい発想や独自の進化が芽吹く。これは単なる保護ではない。国の基礎体力を取り戻すための投資だ。
関税によって安い輸入品との人件費差を埋め、期限付き補助金で国内工場の新設を後押しし、雇用を条件にした支援を行う。税制優遇は歪みを避けるために透明性を持たせつつ、重点分野に限って活用する。政策が本気を出せば、国内回帰は十分に可能だ。
結び
日本はゼロからの発明ではなく、既存知を磨き上げて世界を驚かせてきた。ガラケーも、ウォークマンも、新幹線も、電卓も、リチウムイオン電池も、すべて「妄想を形にする力」の産物だった。
その誇りを思い出そう。そして「ドラえもんを夢見なくなった国」にもう一度、ドラえもんを夢見る余裕を取り戻そう。製造業を国内に呼び戻し、妄想と試作を繰り返す土壌を再生することこそが、未来の日本を再び技術立国として輝かせる唯一の道だ。
名ブタでした。


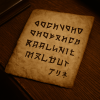





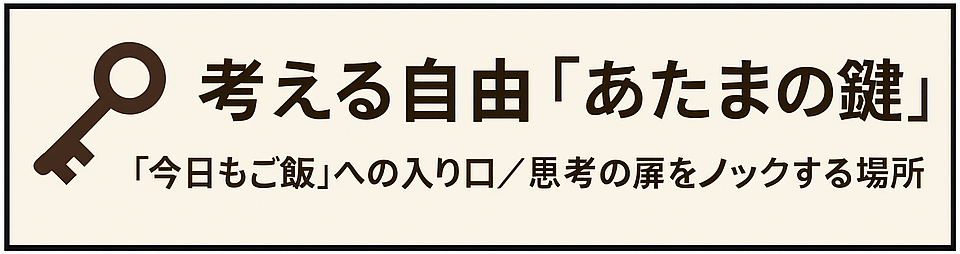
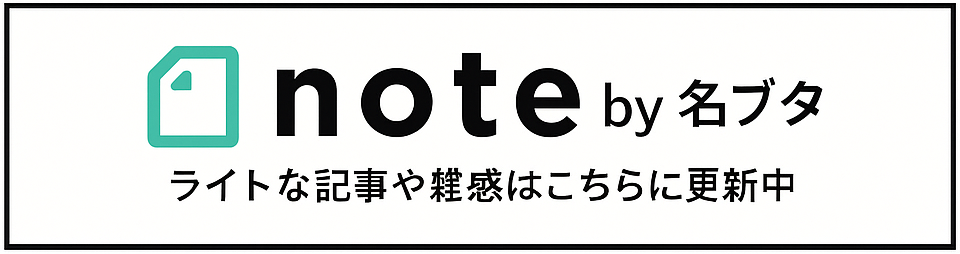
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません