物々交換は存在しなかった?──その否定を否定する!
ー 需要と価値のバランスで、人類は物々交換を生き抜いた

どうも、名ブタです。
あるとき、とあるインフルエンサーがYouTubeで、「昔は物々交換」を否定していたんだよね。
有名YouTuberが政治経済系のコンテンツ内で「昔は物々交換だった」という説明をしていたらしく、それを「そんなものはデタラメだ」と一刀両断してた。
僕はそれを聞いて「なるほど一理ある」と思ったわけ。
正直、この事を真面目に考えた事がなかったから、「ほんとうにそうか?」という疑問が僕の中でムクムクと湧いてきたってわけですよ。
よくある物々交換の物語
昔は物々交換の話ってのは、昔は通貨がないってところから来てるよね。
でも、通貨が無くても人間は経済活動を行う。つまり、人同士の取引が無くなるわけじゃない。
そうすると通貨の代わりに何を使っていたのかと考えると、単純に自分が持っている物との交換という発想になるわけだね。
果物と肉、肉と壺と言った感じで交換していたんだと言われると、直感的でわかりやすい説明だよね。
否定派の意見
物々交換を否定する人の根拠はこうだ。
-
取引相手に需要がなければ成立しない
-
双方が価値の釣り合いに納得できなければ成立しない
例えば「リンゴ2個と牛1頭を交換してくれ」と頼んでも、相手がリンゴを欲しがらない限り成立しないし、牛1頭とリンゴ2個じゃ割に合わないと断られる。
補足で一つ言っていたのは、例えばバナナを作ってる人はバナナを作ってる時しか交換できないじゃんと。確かにw
なるほど、これは一理あるとうか、まぁそうだよなという感じだ。
需要と価値のバランス
まぁ主張はとても解るやすく簡潔に説明していたので、単純に「等価でなければ成立しない」というのは細かい事は言えば語弊はあるだろう。
なぜなら、需要が強ければ不等でも取引は成立するから。
命の危機で喉が渇いている人なら、水1杯に金塊を差し出すかもしれない。
逆に需要が弱ければ、いくら価値が釣り合っても成立しないこともある。
結局、重要なのは「需要と価値のバランス」なんだね。
つまり、需要と価値のバランスにより取引は成立するのであって、無条件に交換が成立するかのような物々交換は取引不成立の可能性を考慮していない不完全な説だというわけだ。
労働力も“物”である
で、冒頭の疑問に返ってくるわけだけど。
僕は有名YouTuberの”物々交換論を聞いたわけじゃないので、どのような文脈でどのような意味で使われたか解らないので、そちらに対して一切の批判するつもりはない。これはあくまで物々交換論の否定に関する否定だ。
まずは、この文脈における物々交換の定義を解釈しなおして、対処となる”物”の定義を広げてみようと思う。
結論から言えば、物々交換を「物体同士の交換」に限定するから誤解が生まれるんだ。
人間が差し出してきたのは物だけじゃないよな思う。例えば下記のような事柄だ。
-
狩猟への参加=労働力の提供
-
集落を守る=安全の提供
-
子どもの世話=世話の提供
こうした労働や役割も、立派に対価として成立する。「交換の対象」になりえる。
現代の物とサービスの交換で考えると解りやすいだろう。
”労働の対価に賃金を頂く”
”お金を払ってサービスの提供を受ける”
貨幣経済も本質物々交換だということ解るわけだけど、これを持って物々交換は成立すると言うつもりはない。
物の定義を広げたとしても、取引が需要と価値のバランスで決まることに変わりないからだ。
共同体は包括契約
狩猟採集の時代でも、農耕が始まったばかりの時代でも、人偏が集落レベルで生活していた時代で大事なのは「集落全体で生き残れるかどうか」であって、個人や一家族だけで完結できるものじゃなかった。
だから資源も労働力も、集落全体で共有されるのが自然な仕組みだった。
もちろん、食料不足のときには「切り捨てる」ケースもあっただろう。
でも、怪我や障害を負いながら長生きしていた痕跡もあるから、基本は共同体としての”生”だったのではないかな。
共同体での生活ってのは、狩りでも農耕でも互いに労働力を持ち寄り、成果物を共有する感じになると思うのだけど、これは結局のところ一種の取引であって、貨幣がないから物々交換ってことだと思った。
これは、現代の企業でも同じ。商品を直接売る人が居るけど、総務とか事務方にも利益は分配される。
一対一ではないければ、物々交換をベースにした取引が生活に溶け込んでるだけだと思う。
物の取引の時代
もう少し時代が進めば、共同体としての営みは影を潜めることになるけど、貨幣が無い時代はやはり物々交換だと思う。金(ゴールド)と物品の交換は物々交換だし、鉱物と食料の交換みたいな互いの特産などを交換するのも物々交換だ。
結論
「物々交換は存在しなかった」という否定は、一面では正しい。
狭義の「物体同士の直接交換」だけを想定すれば、それは不便で神話的なイメージにすぎないでしょう。
けれど、需要と価値のバランスを考え、さらに労働力や役割まで含めれば──
物々交換は人類史のど真ん中にあった。
というよりも貨幣経済も物々交換だ。
だから僕はあえて言います。
物々交換の否定を、否定する!
では今回はこのへんで。
次回もまた、雑学の深みへ一緒に潜っていきましょう。
名ブタでした。











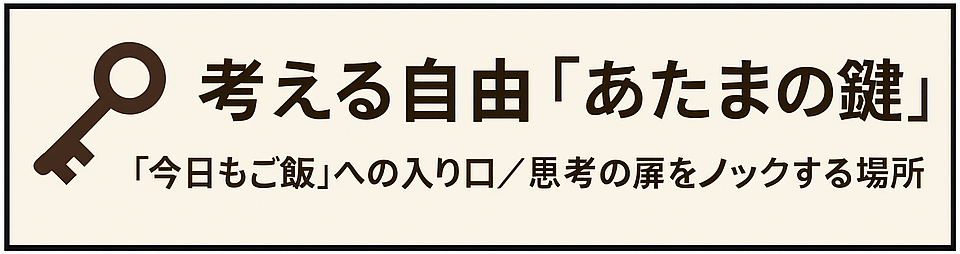
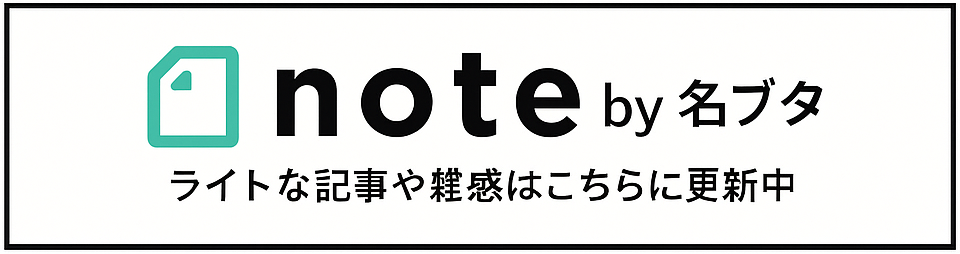
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません