専守防衛のジリ貧を超えて ― 日米安保の影に眠るリスク
徴兵制への恐怖と、既に存在する“戦う覚悟”のリアリティ

どうも、名ブタです。
今回は「日米安全保障条約(以下、日米安保条約)」についての雑学を増やそうと思って調べていたら、ふと考えさせられたテーマがありますので、その話をします。
日米安保条約は1951年のサンフランシスコ講和条約と同時に結ばれたのが始まりで、1960年の改定で今の形が固まりました。条約文には「日本の安全に寄与し、極東における国際の平和と安全の維持に寄与する」とありますが、実際にはアメリカが太平洋の前線基地として日本を位置づけたことは戦略文書や議会発言からも明らかです。要するに「アメリカ本土を守るため」という本音が透けて見える。
まぁ、日本がないと直でアメリカ本土ですし、日本に基地を持つことは太平洋上に沈まない空母を持つようなものなのでしょうね。
この視点に立つと、日本が「アメリカに守ってもらえる」という前提だけで安心していいのか?という疑問が浮かびます。
日米安保に依存する危うさ
戦後日本は「アメリカが守ってくれる」という幻想の上に立ってきました。
第二次世界大戦直後のアメリカなら、戦勝国で世界最強の自負と相まって本気で戦ったかもしれません。
しかし、ベトナム戦争以降のアメリカ人の意識変化を考えると、それはいつまでも続く保証はありません。実際、トランプ前大統領は「なぜ我々が日本を守らなければならないのか」と繰り返し発言しています。
そもそも他国の兵士が日本のために命を捧げる理由はあるのか?冷静に考えれば「誰も他人の国のために死にたくはない」というのが人間の本音でしょう。
そもそもアメリカ人にとって日本は他国。アメリカ本土どころか領土でもないのです。
アメリカが守ってくれるという前提に立つなら、有事の際に「アメリカが穴をあける=日本が滅亡する覚悟」も必要になるのではないか。僕はそう思います。
降伏しても助かる保証はない
では再軍備を避け、いざ戦争になったら「降伏して命を守る」という道を選べばいいのか。そう簡単にはいきません。歴史を振り返れば、無抵抗だからといって民族が助かる保証はどこにもないからです。
ホロコーストを思い出してください。ユダヤ人たちは国家も軍も持たず、武力抵抗できない状況で数百万単位の虐殺に晒されました。
「戦わなければ命は助かる」というのは幻想にすぎません。むしろ理不尽に抗う術を持たないことが、民族そのものを絶滅へ導くリスクになり得る。僕はここを軽視すべきではないと思います。
言い換えれば、抵抗する力を持たないという覚悟は滅びの覚悟も伴うのです。
再軍備と覚悟
再軍備に賛成するなら、子や孫の世代が戦場に行く未来も覚悟しなければなりません。もちろん自分自身にも「命を落とす可能性」を前提とする必要があります。平和に慣れきった僕らにはきつい現実ですが、それを無視した「平和ボケ」の延長では未来は守れません。
このときに多くの人が恐れるのが「徴兵制」です。しかし、現実な路線を考えた場合に、まずは「職業軍人」が厚くなる方向に進むんじゃないかと僕は思いました。
職業軍人とPMCの可能性
戦国時代に織田信長が行った兵農分離が信長躍進の原動力だと聞きます。まぁ実際にはやってないみたいな話も聞きますが、その話は脇に置きましょう。兵農分離は農民が戦時だけ兵士になるのではなく、常時戦闘を専門とする軍人を置くという仕組みです。現代でいえば、自衛隊がその役割を担っています。
さらにその延長線上に見えてくるのが PMC(民間軍事会社) です。海外ではすでに、
-
大使館の警備
-
石油・鉱山など資源開発地の防衛
-
紛争地での要人警護
などでPMCが当たり前のように活動しています。
日本でもPMCを認可する発想を持っていいのではないか、と僕は思います。もちろんリスクはある。外国のスパイがPMCを隠れ蓑に活動する可能性は否定できません。だからこそ認可制と国家との強固な連携が必須になります。国家が正面からは手を出しにくい任務を民間の顔で埋める。これが現実的な再軍備のひとつの形です。
軍隊と言う形では、その活動にはどうしても制限がありますが、民間という形であれば活動の幅が広がります。
こういう話をすると、あまり良い反応はされないかもしれませんが、日本が再軍備に動けば国内での兵器製造もある程度始まる可能性が高いです。そうすると、そういった施設の警備なども民間軍事会社の仕事となるでしょう。
即応予備自衛官という現実
ここで忘れてはいけないのが、すでに日本に存在する「予備自衛官」「即応予備自衛官」という仕組みです。彼らは普段は民間で生活しながら、有事には招集されて即座に部隊に組み込まれる存在です。
僕らが徴兵制に怯えている影で、すでに「いざとなれば戦う覚悟」を持ち、自ら国家に力を貸す立場に身を置いている人がいる。この事実は無視できません。むしろ僕は心から尊敬します。
再軍備の議論はどうしても抽象的になりがちですが、すでに現場には覚悟を決めている人たちがいる。その上でPMCのような民間組織が整えば、国防の多層化が進み、最悪の道を避ける現実的な力になるのではないでしょうか。
結論
日米安保に依存するだけでは未来は守れません。降伏すれば助かる保証もない。だからこそ、自分たちで戦う覚悟が必要です。
その覚悟は空想の話ではなく、すでに即応予備自衛官のように現場で体現している人たちがいます。職業軍人やPMCは、その覚悟をさらに支える現実的な仕組みになるでしょう。
専守防衛のジリ貧を超えるには、アメリカに守られる幻想ではなく、日本人自身の「守る意思」に向き合うことが求められているのです。
その意思をどう次の世代へ引き継ぐか――それが僕らに課された課題ではないでしょうか。
名ブタでした。
追記
この記事の執筆を終え、掲載しようとしていた矢先に、ウクライナから衝撃的なニュースが飛び込んできました。
まず、亡くなられた女性記者のご冥福を心よりお祈りいたします。
報道によれば、取材中にロシアに拘束されたウクライナの女性記者が死亡し、その遺体からは拷問の痕や眼球の摘出が見つかったといいます。さらに拘束後の食事は劣悪で、行方不明者も他に存在するとのことです。
これは「降伏しても命が助かる保証はない」という僕の論と深く通じる出来事です。非戦闘員であるはずの記者でさえ、人道的に扱われることなく、拷問を受け、命を奪われた。例え民間人でも占領や拘束は安全の保証ではなく、むしろ暴力の支配の始まりであることを示しています。
戦後に国際社会から批判が集まったとしても、その時点で失われた命は戻りません。強姦や略奪もまた、戦闘に巻き込まれたと処理されてしまえば終わりです。現実の戦争はそうした理不尽さに満ちています。
改めて、この事件は「抵抗できる力を持つこと」の意味を僕に強く突きつけました。守る意思を持たないということは、ただ生き残ることではなく、理不尽に奪われるリスクと背中合わせなのです。









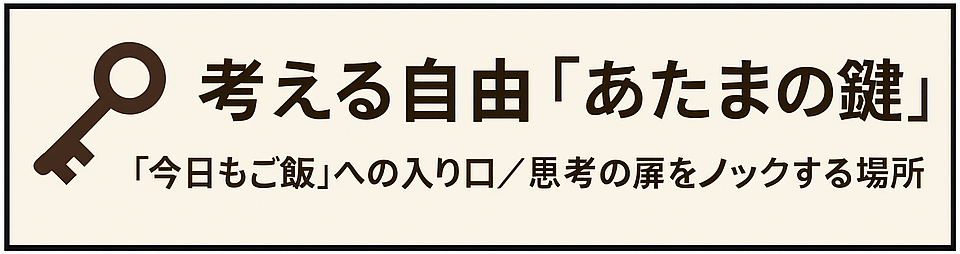
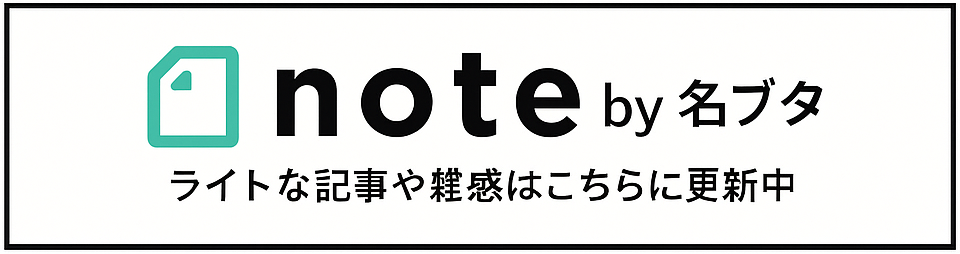
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません