読み聞かせの可能性を考える #1|“読む”ではなく“聞く”が育てるもの
― 映像では補えない、共感と想像の教育効果を探る ―

どうも、名ブタです。
「読み聞かせ」って聞くと、小さな子どもに絵本を読んであげる光景を思い浮かべる人が多いと思います。
でも、最近僕はふとこう思ったんです。
読み聞かせって、実はもっと深くて、人間の“脳”や“心”に働きかけてるんじゃないか?
それは単なる親子のコミュニケーションではなく、
「人間が“人間らしくなる”ための仕組み」なんじゃないかと。
読み聞かせがもたらす力
読み聞かせは、子どもに対していくつもの能力を同時に育ててくれます。
-
語彙力の向上
普段の会話では出てこない言葉に触れる機会になる。 -
想像力の活性化
絵があっても、物語は自分の頭の中で補完していく。 -
集中力と聞く力
話をじっくり聞く経験は、学習や人間関係の土台になります。 -
感情理解・共感
登場人物に感情移入することで、他者理解が深まる。 -
親子・大人との信頼形成
「読んでもらう」という体験そのものが、愛着の基盤になる。
つまり、「読み聞かせ」は脳と心の両方を育てる、非常に多面的な営みなんです。
映像コンテンツとの違い
では、YouTubeなどの映像で代替できるのか?
僕は実感も含めて、そうは思いません。
映像は「情報が完成された形で与えられる」ため、受け手は想像や補完をしなくても物語を理解できます。
一方で、読み聞かせは情報が“未完成”だからこそ、脳が能動的に働く余地が大きい。
また、映像ではセリフや表情は目に見えるけど、そこに双方向性や情緒の共有は生まれにくい。
それが読み聞かせでは、読み手の声の抑揚や「間」、近くにいるという感覚が、深い共感や安心感につながっていくんです。
紙芝居や絵本は、“見るもの”ではなく“体験するもの”
たとえば、紙芝居。
「動画で見ればいいじゃん」と思うかもしれないけど、実際はまったく違います。
紙芝居の本質は、“その場にいる”こと。
-
読み手と聞き手の間に空気があって、
-
間があり、視線が交わり、
-
子どもたちの笑いやざわめきが混じりながら、
-
一緒に物語を「体験」している。
それを映像にした瞬間に、その共在感は切れてしまう。
リアルな場では、無意識に他者の動きや表情を読み取り、ミラーリング(模倣)し、共鳴していくのに、映像ではそれがうまく働かない。
現代の技術ではまだ、「人と人が向き合っている感じ」までは再現できないんですよね。
リモート社会の知見が、この感覚を裏付けてくれた
この“場の体験”がいかに大きな意味を持つか。
それを裏付ける現象が、近年の社会変化の中で明らかになってきました。
コロナ禍による在宅勤務やオンライン会議の普及により、
人と人が画面越しに話す時間が増えたことで、共感や一体感の欠如が浮き彫りになったのです。
実際、脳科学や心理学の領域では、共感を司る脳の部位が、画面越しではあまり活性化しないという研究結果も出ています。
これは僕の予想通りでした。
人間は、言葉だけでなく、相手の動きや目線、声の間合い、仕草など、あらゆる非言語情報を無意識に読み取りながら「感じている」ものです。
その多くが、オンラインでは遮断されてしまう。
アメリカで出社回帰の動きが加速しているのも、こうした“共感の欠如”に対応しようとする流れの一部ではないかと感じています。
もちろん、将来的にメタバース環境の向上やアバターの動きが高度化して、
視線の共有や身体的なリアルさが再現されるようになれば、画面越しでも共感が生まれる環境は整っていくかもしれません。
でも、もしかしたら人間が発する微弱な電磁波とかを感じ取ってるかもしれないけどね。
いずれにしても、今の時点では、紙芝居や読み聞かせのようなリアルな「体験」は、まだ失われてはならない大切な営みだと、僕は思うのです。
名ブタでした。









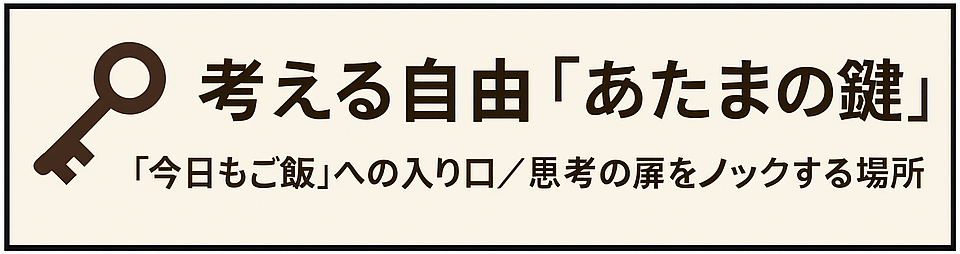
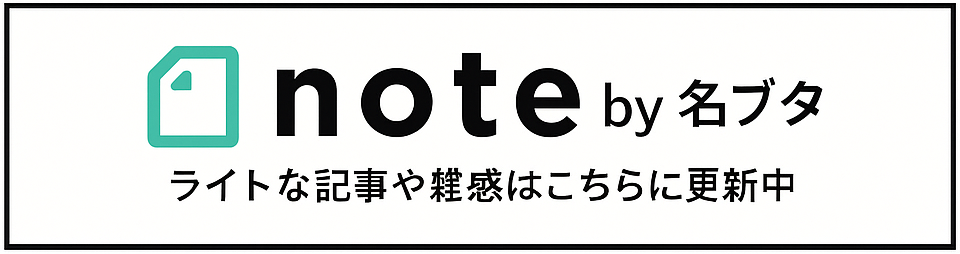
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません