人材紹介制度における管理職の紹介手当、もらっていいのか?
― 信頼で動く制度を、信頼だけで支えてはいけない理由 ―

どうも、名ブタです。
今回は「人材紹介制度において、管理職が紹介手当を受け取ることは許容されるのか?」というテーマについて考えてみます。
最近はリファラル採用の方が伝わるのかな?
一見すると制度の運用範囲を広げるだけの話にも思えますが、実は組織の信頼構造やガバナンス体制に大きく関わる重要な論点です。
僕は、この問いに対して否定的な立場を取っています。
その理由を、制度の構造・倫理・運用リスクの観点から整理していきます。
前提:肩書きと権限は一致しない
まず補足しておきたいのは、「管理職=採用決定権を持つ人」という単純な図式ではないという点です。
実際の現場では、係長や主任といった非管理職クラスの職位であっても、実質的に採用の判断に関与しているケースがあります。
一方で、課長職以上であっても採用に一切関与しない立場であることもあります。
本記事では、「採用判断に影響を及ぼしうる立場」の人間を広義に“管理職”と定義して論じていきます。
線引きの本質は肩書きではなく、影響力の有無にあります。
制度に潜む“相反行為”のリスク
紹介制度は、「社内の信頼を活かした採用手段」として多くの企業で活用されています。
ところがそこに**金銭的な報酬(紹介手当)**が発生すると、制度の性質が微妙に変質します。
特に管理職が制度を利用する場合、問題は次のように発生します。
-
採用に関与する立場であるにもかかわらず、自分の利益が絡む
-
実際に判断していないとしても、「判断に影響を与えたのでは?」と見られやすい
-
それが疑念を生み、制度全体への信頼を損なう
これはまさに、**利益相反(conflict of interest)**の構造です。
制度は“正しく運用されたか”ではなく、“誰の目にも公正に見える構造かどうか”が問われるのです。
「他部署が審査すればいい」の限界と共謀リスク
「管理職が紹介しても、審査は別の部署がやればいい」
これは一見、問題を回避できるように思えますが、実際には不十分です。
-
管理職という立場は部署を越えて影響力を持ちます
-
「先輩」「上位役職者」の紹介を断りにくいという心理的圧力がかかります
-
表面的には別部署の判断でも、**裏での“共謀”や“便宜の交換”**が発生するリスクがあります
こうした構造は、外からは非常に見えづらく、制度設計の時点で“共謀の余地”を排除しておく必要があるのです。
善意は未来を保証しない
僕自身、過去に人を紹介したことがあります。
そのとき上司から「紹介手当を出そうか?」と言われましたが、受け取りませんでした。
けれどそれは、たまたまそのときの僕の状況と倫理観が「受け取らない」という判断をさせただけです。
もし僕が多額の借金を背負っていたり、会社に強い不満を抱いていたらどうなっていたでしょう?
信頼は大事です。でも、制度は信頼だけに依存してはいけない。
制度とは、「信じている人を、信じ続けるための仕組み」であるべきです。
線引きがあるから止められる
もちろん、「じゃあ平社員はいいのか?」という疑問は出るでしょう。
平社員やパートだって、不正に関与する可能性はあります。
それこそ部下だけど義理の父で…なんて事例もゼロではない。
でも大事なのは、
-
不正が発生したときに異常に気づけるか
-
そしてそれを止められるかどうか
たとえば、平社員と課長の共謀だったとしても、継続的な不審行動があれば気づける余地があります。
さらに、「管理職は手当対象外」という明文化されたルールがあれば、
高位の役職者が関与していたとしても**“制度違反”として止める根拠になる**。
線引きがあるからこそ、止める力が働くのです。
すべてのリスクに線を引くのは不可能です。
だからこそ、現実的に影響力が大きく、制御しやすいポイントに線を引くことが制度設計として重要になります。
その象徴的な区切りが、「管理職」というラインなのです。
管理職は、制度を守る側に立たなければならない
管理職という立場は、制度の恩恵を受けるよりも、制度の健全性を守る側であるべきです。
報酬や評価で優遇される代わりに、利害が発生しうる場面から一歩引く義務がある。
それが、組織における牽制機能であり、コーポレートガバナンスを支える柱です。
そして最後にもう一度。
制度とは、信頼できる人を、信じ続けていくために作るもの。
名ブタでした。🐷📜



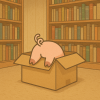







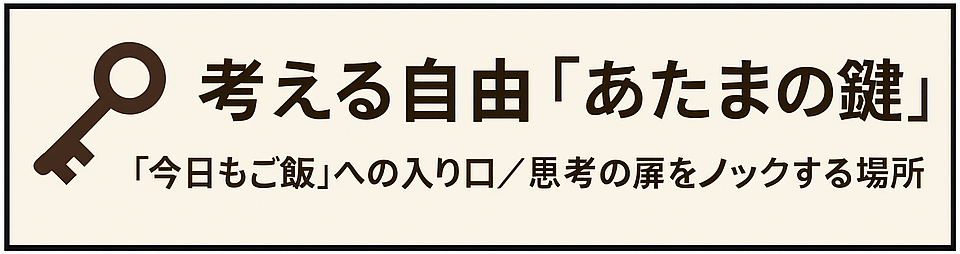
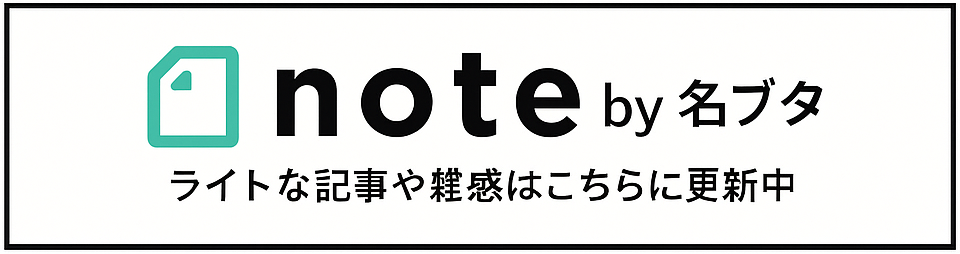
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません