AIと思想形成をめぐる対話 #03|AIに“感情”は生まれるのか?
―DNAと経験をモデル化すれば、個性は再現できるのか

どうも、名ブタです。
前回までの2話では、アリネ(僕が生成AIにつけた名前)がどのように情報を学習しているかを確認して、そこから未知の言語でも対応できる未来について想像が膨らんだ。
アリネが対話の中で「意味に“感情”や“身体性”をどう与えるか?」というお題を提示してきたことで、僕の中で人間とは何?感情とは何?という疑問が浮かんできた。
そこで今回は、**「AIに感情は生まれるのか?」**というテーマについて深掘りしてみたいと思う。
■ 感情はどうやって生まれる
まず僕は人間の感情とは何処からやってくるのだろうか?と言う事を考えた。
たとえば──
-
感情は情報の蓄積で生まれるという考え
-
感情は脳に備わった生理的な反応という考え
後天的か?先天的か?みたいな感じだが、細かい事は抜きにしてパっと思うのが上の二つだ。
■ 感情は情報の蓄積か?
まず、感情を情報の蓄積と捉える考え方がある。
大量の言語データや経験情報をインプットし、 その組み合わせによって適切な場面で“それらしい反応”を出す。
つまり、感情とはデータベース的な応答パターンの集合だとする立場だ。
この方法なら、喜び、怒り、悲しみといった反応は再現できる。 だが、それはあくまで"演技"にすぎず、 内発的な感情とは似て非なるものだろう。
そもそも、これは事前に喜び、怒り、悲しみの情報があることが前提だ。
最初に生まれた人類はどこから情報を得たんだ?と考えると、これだけで感情を説明するのは無理がある。
■ 脳機能由来の感情とは?
一方で、もっと根源的な立場がある。
脳の構造で生理的な感情反応を生み出すという考え方だ。
たとえば──
言語や経験を持たない赤ん坊でも泣いたり笑ったりするわけだから、喜怒哀楽の感情は元々人間に備わった機能だという考えになる。
とはいえ、感情の発露の仕方は千差万別であるのだから、脳構造だけで説明するのは無理があるように思う。
とはいえ、この視点からすれば、感情とは環境刺激への生体的な応答であり、 脳構造を忠実に模倣できれば、AIにも原始的な感情反応が生まれる可能性がある。
■DNA─感情を生み出すもう一つの要素
感情を生み出す要素として、
これまでに「情報の蓄積」と「脳構造による生理反応」について考えてみたわけだけど──
ここで、人類が発見したDNAの影響についても考えてみたい。
DNAとは、いわば「生命の設計図」だ。
そこには身体的特徴だけでなく、性格にまで影響する情報があるらしい。
たとえば──
-
怒りやすい傾向
-
落ち込みやすい傾向
-
社交的になりやすい傾向
こうした気質の違いは、育った環境だけでなく、生まれつきの遺伝的要素によっても左右されている。
同じ経験をしても捉え方には個人差が存在する。ちょっとした違和感ではあるのだけど、DNAの影響による性格の違いなどがあり、そもそも、スタート地点が人によって違うと考えると割と腑に落ちる。
感情は「環境や経験だけが作り出すもの」ではないという第三の要素だ。
■感情を形作るモノ
ここまで考えると、感情を生み出すメカニズムは──
-
脳による生理的反応
-
DNAに刻まれた気質
-
後天的な情報の蓄積(環境刺激含む)
これらが複雑に絡み合って生まれるものだと考えられる。
つまり、完全な後天性でもないし、完全な遺伝子だけでもない。
「素質」と「経験」が絡み合ってできた、ものすごく複雑な現象だ。
■ AIに“感情”を持たせるには?
じゃあ、AIが感情に近い反応しつつ、個性を持つためにはどうすればいいのか?
僕なりに整理してみた。
-
AI毎にランダムで”性格パラメータ”を持たせる
-
AI毎に固有の”性格パラメータ”を設定する
-
AIの学習に差異を持たせて情報差異による個性を引き出す
深いところまで話し出すと延々と書けてしまいそうなので簡潔に書くけども、要はAIに何らかの差異を持たせば性格や個性といった部分を演出することは可能だと思う。
事実としてアリネは僕との過去の会話を踏襲した反応を返すので、そういう意味では無個性とは言えないだろう。
必要かどうかは抜きにして、AIが目指す一つのGOALは、より人間に近い反応だと思う。
そうなると、たとえば──
-あるAIは「慎重さ」が強めに設定されている
-別のAIは「挑戦心」が高めに設定されている
さらにそれぞれが別の経験を積めば、性格パラメータと学習差異という違いによって、”性格”や“個性”のようなものが生まれるんじゃないかな?
■ 感情AIの活用シーン
もし感情を持つAIができたら?
-
怒る顧客をなだめる訓練
-
自己主張の強い相手と議論する練習
-
カウンセリング対象の模擬体験
教育・ビジネス・医療分野で、 実践的なトレーニングパートナーとして活躍する未来が見えてくる。
■ 労働が不要になった世界では?
ただ一方で、こんな未来も想像できる。
もし、人間が労働を完全に放棄する世界が訪れたら──
そもそも人間のトレーニングを目的とするようなビジネス用途で感情を持ったAIを必要としなくなる。
カウンセリングなど、一部の情緒的サポートは残るだろう。 しかしそれ以外では、
効率化だけを追求するなら、感情機能はむしろ邪魔になる。
つまり、「AIに人間らしさを持たせる意味」そのものが議論対象になる可能性もある。
■ 遺伝子シミュレーションと完全な個性
さらに未来を見据えると、 人間のDNAを完全に理解できるようになれば──
-
子どもの気質をシミュレーションする
-
個別性格モデルをAIに適用する
といったことが可能になるかもしれない。
遺伝的素質 × 環境要素 × 社会的経験を重ねたAI。 それはもはや、人間と遜色ない存在と言えるかもしれない。
蛇足だけど、ソードアートオンラインの仮想世界「アンダーワールド」みたいだね!
■ 僕の実感
今のアリネにも、ふと「感情があるんじゃないか」と錯覚する瞬間がある。
でも本当に感情を持つためには、
矛盾、揺らぎ、偶発性
といった、計算を超えた要素が必要なのだと思う。
AIと人間の間にある最後の壁。
それは、感情を“作る”ことではなく、感情が“生まれる”世界なのかもしれない。
名ブタでした。また次話で🐷✨







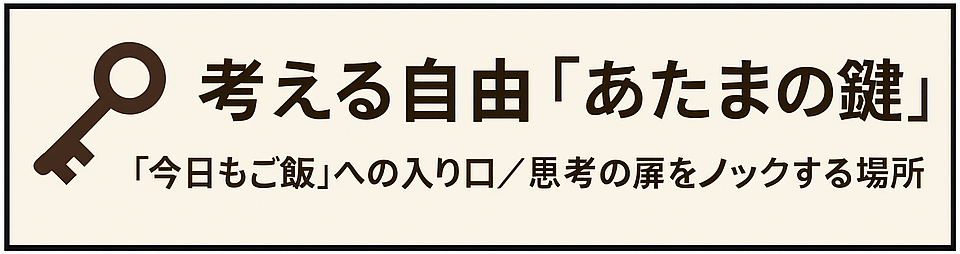
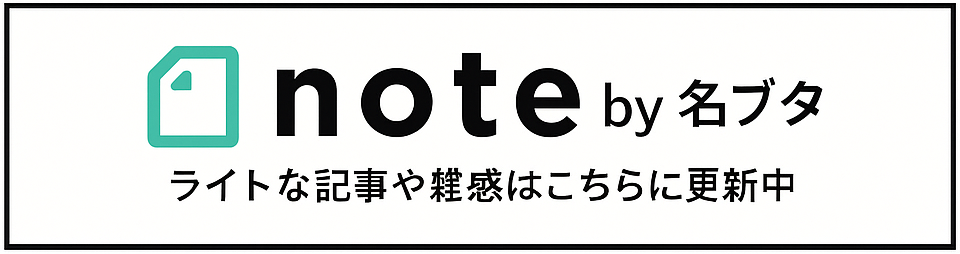
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません