読み聞かせの可能性を考える #2|“紙芝居”のポテンシャル
― 読まれない子”にも届く、紙芝居という語りの力 ―

どうも、名ブタです。
前回は、「読み聞かせ」がただの親子の触れ合いではなく、
“人間が人間らしくなるための仕掛け”として、脳や心に深く作用する営みなのではないか?
という視点から、その効果や育まれる力について考えました。
今回はその続きを少し広げて、
家庭の外でも通用する読み聞かせの力と、
子ども以外──つまり大人にも効く読み聞かせの効果について話をしてみたいと思います。
家庭で読み聞かせをされない子どもたちに、どう届けるか
なにかで絵本の読み聞かせをする家庭が減ってると聞いたことがある。
いま、家庭内で読み聞かせを受ける子どもは減っています。
親の忙しさや、スマホ・タブレットの普及、書店の減少・・・
そもそも“読み聞かせ文化”自体が、すでに特別なものになりつつある時代なのかもしれない。
でも、読み聞かせが「聞くこと」で育つ力をもつなら、
その恩恵を受けられるのは家庭に限らなくてもいいはず。
そのとき、ひとつの鍵になるのが──紙芝居という存在。
紙芝居のもうひとつのポテンシャル
紙芝居は、「読み聞かせ+視覚」というハイブリッド。
しかも、見る・聞く・間(ま)を楽しむという構造上、
能動的に「聞き入る」仕掛けが自然と組み込まれている。
読み聞かせに慣れていない子どもでも、
絵があることでストーリーに引き込まれ、
語りのリズムや声の抑揚を自然に受け取ることができる。
家庭での読み聞かせがなかったとしても、
紙芝居という“公共的な読み聞かせ”なら、その体験は届く。
これは、読み聞かせの持つ教育力を、家庭の外に開いていくための大きな可能性だと思う。
読み聞かせは、大人にも効くらしい
しかも最近、こんな話もある。
読み聞かせの効果は、子どもだけじゃない。
実は、成人に対しても集中力や共感性、想像力を刺激するという報告が出ている。
たとえば、演劇的な読み聞かせや、ボランティアによる音読活動では、
高齢者がリラックスし、会話が増え、情緒が安定したという事例もある。
つまり読み聞かせは、“聞いて育つ”力を、一生通じて活かすことができる行為なんだ。
聞くことで、心が耕される
本を読むだけでは届かない“何か”を、
人の声は伝えてくれる。
読み聞かせは「読む」だけではなく、
“聞く”という行為の中に、人格形成に関わる重要な要素が宿っている。
それは子どもに限らず、大人にも──社会全体にも影響する力かもしれない。
そんなふうに考えると、
読み聞かせって、やっぱりすごい営みなんだなって思う。
名ブタでした。











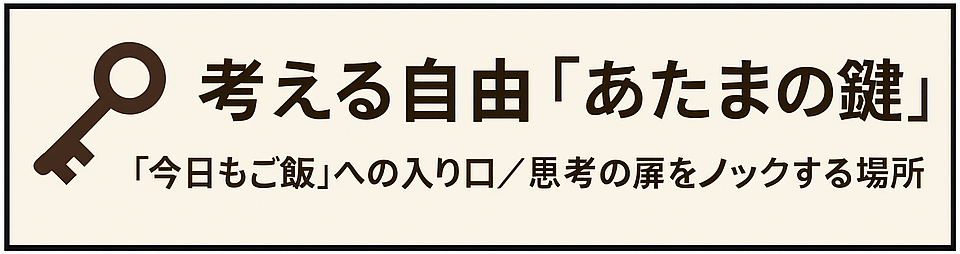
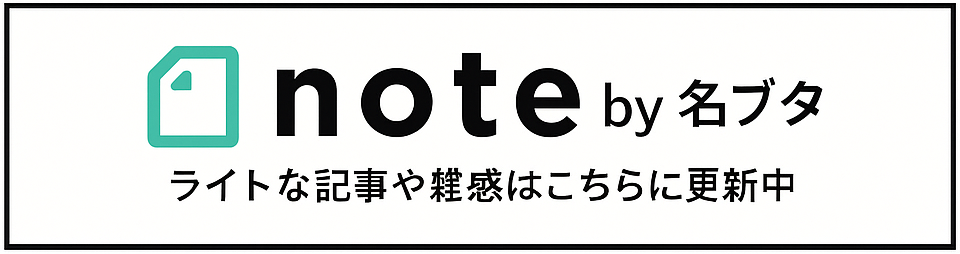
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません