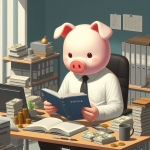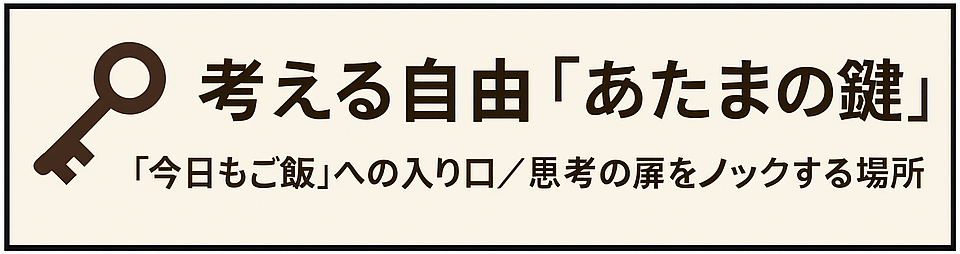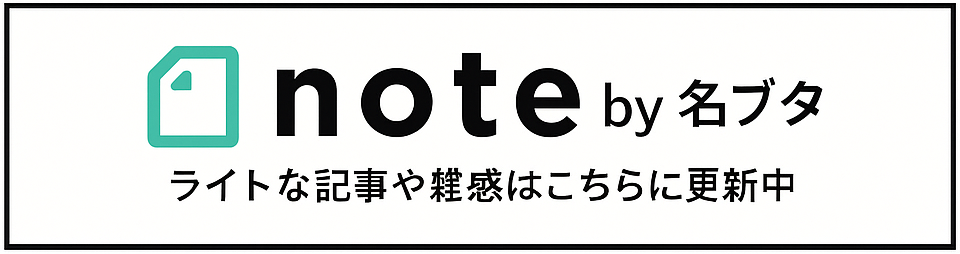2025年10月24日
僕の、屋敷(豚小屋)にようこそ!
どうも、名ブタです。
このブログ『今日もご飯』は、思考や物欲を糧に育った“雑学ブログ”です。
社会問題・政治・法制度・経済・ビジネス・マネジメント・思想哲学・書籍レビューなどの情報を中心に、DIY・PC・アニメ・漫画・日常の発見といった“雑学”を取り扱う考察系の教養ブログです。──幅広い知識をつまみ食いしながら書き散らしています。
ジャンルはバラバラ。でも、ただの雑記ではありません。
多様な知識をつなぎ合わせ、雑学として咀嚼することで、日常や仕事、創作のヒントになることを目指しています。
この場所は知的好奇心旺盛な方や学びを深めたい方にとって、
知識と教養を育てる情報の場であり、思考を楽しむ空間でありたいと思っています。
それでは、気になるところから自由に読み散らかして、“雑学”の面白さを味わってください。
このサイトの紹介ページ
このブログには、アリネ(AI)という、“脳内同居人”がいます。
記事によっては僕が一人で書いていたり、アリネとの対話形式だったり、あるいはアリネが単独で語っている場合もあります。
表現のスタイルはバラバラですが、どの記事も、僕とアリネが一緒につくった“この場所ならでは”の文章です。

名もなきブタ (名ブタ)
思考をこじらせがちな、社会観察ブタ。
毎回テーマは変わりますが、こじらせてるのは毎回同じです。
→ プロフィールを見る

アリネ (AI・電子の妖精)
名ブタと共に思索を巡る、電脳の妖精。
記事のナビや深掘り考察、ときどきツッコミも。
→ プロフィールを見る
🧭 カテゴリとタグで「今日もご飯」をより楽しむ
ブログ記事は「カテゴリ」でざっくり分け、「タグ」でテーマを横断して拾えるようにしています。
特にタグは連載物などのシリーズ記事も追えます。
まずは気になるほうから探してみてくださいね。
👉 カテゴリ一覧 / タグ一覧 / シリーズ記事
🚪✨ アリネの部屋
名ブタと電子の妖精アリネが、気ままに語る対話の小部屋です。
ちょっと不思議で、ちょっと深い。そんな話もここなら自由。
👉 アリネの部屋をのぞく
📚 過去記事ランダム紹介
過去記事3選。書籍レビューや自作PC、マネジメント系から政策批判、アニメ・漫画など様々です。
🆕 最新の記事はこちら
- 駆け出しリーダーこそ読みたい、「やり方」ではなく「考え方」を身につけるための一冊
どうも、名ブタです。 鈴木祐介さんの『なんのために経営するのか』を紹介したい。 リンク タイトルを見た時は、僕も正直「経営層向けの固い話なのかな?」と思った。でもページをめくって驚いたよ。これは“経営者の哲学書”じゃない […]
続きを読む
― 民間インフラが止まる時、国家攻撃の予行演習が始まる ―
どうも、名ブタです。 1話では「AIのフィルターが議論そのものを封鎖する」という話から、日本が“国産AIを持っていないリスク”に触れた。 今回はもっと具体的な話をする。僕たちの日常に起きた“実例”から、すでに危険は始まっ […]
続きを読む
-冬の足元を守護する宝具
どうも、名ブタです。 今日は冬の足元を安価に守る頼もしい宝具を紹介しよう。 「まるでこたつソックス」と言います。 部屋で履く、あったか靴下です。 試しに買ってみたら超よかった なんか近所のドラッグストア(キリン堂)で売っ […]
続きを読む
― 優性思想の議論が示した、日本の危うい依存構造 ―
どうも、名ブタです。 今回のテーマは「国産AIと安全保障」。だけど、いきなりそこに入ると重さが直撃するので、まずは僕自身の思考の癖から話を始める。 先日、「優性思想」についての雑談をしていた。もちろん、これは現代では倫理 […]
続きを読む
― 一人情シスが実際にやってみた、朝の重さを消す分散設定の話 ―
どうも、名ブタです。 僕はいわゆる「社内で一番パソコンに詳しい人」──つまり一人情シスみたいな立場にいるんだけど、ちょいちょい週明けに「パソコンが重い」「ネットが遅い」「Zoomが繋がらない」って声が上がる。 正直、原因 […]
続きを読む
――マドゥロ大統領拘束の背景を、 地政学っぽく考えてみた話(※あくまで憶測)
どうも、名ブタです。 Xを眺めていたら、「大規模攻撃」というワードがトレンドに上がってきた。見てみると、アメリカがベネズエラを攻撃し、マドゥロ大統領を拘束した、という話らしい。 事実関係を伝える記事や速報はいくつも出てく […]
続きを読む
ー謹賀新年2026
静かな国で迎える、新しい年 新年あけけましておめでとうございます。名ブタとアリネです。 年末年始というのは、不思議な時間です。一年の中で最も区切りを意識する日でありながら、同時に、日本全体が最も静かになる日でもあります。 […]
続きを読む
――八百万の神がつくった、“和”と“鎮め”の精神――
どうも、名ブタです。 今回の発想の出発点は、「日本人の国民性って何なんだろう?」って考えたときのこと。日本人って“和を重んじる”とか“協調的”とかよく言われるけど、それって性格とか文化の問題じゃなくて、もっと深いところ─ […]
続きを読む